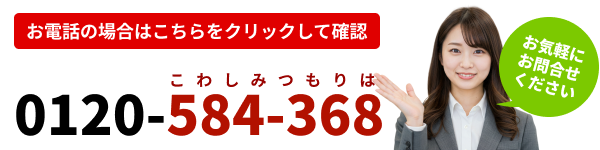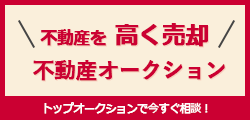自宅や所有物件の解体工事を前に、「アスベストレベル3が見つかったらどうしよう…」と不安に感じていませんか?あるいは、解体工事の元請業者様で、「法改正後の正しい撤去方法を再確認したい」とお考えではないでしょうか。
アスベストレベル3の撤去は、近年の法改正で規制が強化されており、正しい手順と知識が不可欠です。ご安心ください。この記事では、数々の解体工事をサポートしてきた専門家の視点から、具体的な撤去方法、費用相場、そして信頼できる業者選びのポイントまで、必要な全知識を網羅的に解説します。
まず、この記事でお伝えする結論の要点をまとめました。
- レベル3とは: 発じん性が比較的低い、スレート屋根や石膏ボードといった固い建材に含まれるアスベストです。
- 撤去の基本: アスベストを飛散させないための「湿潤化」と、建材を壊さずに取り外す「手ばらし」が原則となります。
- 全6ステップ: ①事前調査 ②計画・届出 ③養生 ④除去 ⑤清掃・廃棄 ⑥記録 という手順で安全に進めます。
- 届出の要否: 基本的に国への届出は不要ですが、「みなし工事」や自治体独自の条例で必要になる場合があるため注意が必要です。
- 費用相場: 数万円から数十万円規模が目安ですが、作業内容や面積によって大きく変動します。
- 業者選び: 失敗しないためには、複数社の相見積もりを取り、実績をしっかり確認することが最も重要です。
なぜ、これほどまでに正確な知識が求められるのでしょうか。それは、知識不足のまま工事を進めてしまうと、法令違反による罰則や、アスベスト飛散による健康被害など、取り返しのつかない事態を招く重大なリスクがあるためです。
実際に、「届出が不要だと思っていたら、実は自治体の条例で必要だった」というケースや、「費用が安いという理由だけで業者を選んでしまい、不適切な工事をされた」といったトラブルは後を絶ちません。
本記事を最後までお読みいただければ、そのような失敗を未然に防ぎ、安全かつ適正価格でレベル3撤去を完了させるための全ての知識が身につきます。安心して工事を進めるための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
当サイトでは、複数の企業と提携し情報を提供しており、当サイトを経由して商品またはサービスへの申込みがあった場合や、当サイトへの情報掲載に関して、各企業から支払いを受け取ることがあります
アスベストレベル3とは?レベル1・2との違いをわかりやすく解説
アスベスト(石綿)と聞くと、漠然と「危険なもの」というイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、実はアスベストが含まれる建材は、その危険度に応じて3つのレベルに分類されています。
なぜ、このレベル分けが重要なのでしょうか。
それは、レベルによって法的な規制や、求められる作業の厳重さが大きく異なるためです。これから解体や改修工事を行う建物にどのレベルのアスベストが存在するのかを正確に把握することが、安全な工事計画を立てるための最初の、そして最も重要な一歩となります。
アスベストレベル3の具体的な建材例
アスベストレベル3に分類される建材は、比較的硬く、セメントなどで固められているものがほとんどです。私たちの身の回りの建物の、意外と多くの場所で使われています。
- 屋根材: 戸建て住宅でよく見かける波型の屋根材(コロニアル、カラーベストなど)
- 外壁材: サイディングと呼ばれる板状の外壁材
- 床材: 学校や店舗の床でよく使われる硬いビニル床タイル(Pタイル、コンポジションビニル床タイル)
- 内装材: 天井や壁に使われる石膏ボード(ビニル壁紙が貼られていることが多い)
- その他: 煙突の材料や、水道管のつなぎ目に使われるパッキンなど
これらの建材は、通常の状態ではアスベストが飛散する可能性は低いですが、割れたり、砕けたりすると内部からアスベスト繊維が露出する危険性があります。
【比較表】レベル1・2との危険度と規制の違い
レベル3の位置づけをより明確に理解するために、最も危険なレベル1、次に危険なレベル2と比較してみましょう。発じん性(危険度)が全く異なることがわかります。
| レベル | 発じん性(危険度) | 主な建材例 | 作業レベルの名称 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 著しく高い | 石綿含有吹付け材 | 発じん性が著しく高い作業 |
| レベル2 | 高い | 保温材、耐火被覆材、断熱材 | 発じん性が高い作業 |
| レベル3 | 比較的低い | スレート屋根、Pタイル、サイディングなど硬い建材 | 発じん性が比較的低い作業 |
なぜレベル1・2は特に危険なのか?
レベル1に分類される「吹付け材」は、綿のような状態で天井や壁に吹き付けられています。非常に脆く、少しの衝撃でもアスベスト繊維が広範囲に飛散してしまうため、最も危険度が高いとされています。
レベル2の「保温材」や「断熱材」は、配管やボイラーなどに巻き付けられていることが多く、こちらも劣化すると崩れやすく、繊維が飛散しやすい性質を持っています。
これらのレベル1・2の建材は、撤去作業の際に厳重な隔離措置や高性能な保護具が法律で義務付けられており、作業計画を事前に行政へ届け出る必要もあります。
このように、アスベストレベル3は、レベル1・2と比較すると危険性は低いとされています。しかし、法規制の対象であることに変わりはなく、油断は禁物です。
次の章では、このレベル3建材を具体的にどのように撤去していくのか、安全に作業を進めるための全6ステップを詳しく解説していきます。
【全6ステップ】アスベストレベル3撤去方法の完全手順フロー
アスベストレベル3の撤去作業は、安全と法令遵守を両立させるために、決められた手順に沿って進めることが絶対条件です。基本となるのは「①事前調査」「②計画・届出」「③養生」「④除去」「⑤清掃・廃棄」「⑥記録」という6つのステップです。
なぜなら、これらのステップのいずれか一つでも省略したり、手順を誤ったりすると、アスベストの飛散による健康被害や、法律違反による厳しい罰則につながる危険性があるからです。
ここでは、各ステップで具体的に何をすべきなのか、その内容を一つひとつ詳しく見ていきましょう。
ステップ1:事前調査(全ての工事で義務)
まず最初に行うのが、アスベストが「どこに」「どのくらい」「どのような状態で」使われているかを調べる事前調査です。2022年4月の法改正により、解体・改修工事を行う際は、規模の大小にかかわらず全ての工事でこの事前調査が義務付けられました。
調査は、まず設計図書などの書類で確認する「図面調査」を行い、その後、現地で直接建材を目で見て確認する「現地目視調査」を実施するのが基本の流れです。
ステップ2:作業計画の作成と届出
事前調査の結果に基づき、具体的な作業手順、安全対策、作業員の役割分担などをまとめた作業計画書を作成します。この計画書は、作業員全員が安全な作業方法を共有し、工事をスムーズに進めるための設計図となる非常に重要なものです。
計画書には、以下の内容を盛り込みます。
- アスベスト含有建材の場所と種類
- 除去作業の具体的な手順
- 作業員の保護具の種類と使用方法
- 廃棄物の処理方法
- 緊急時の連絡体制
なお、レベル3の撤去作業自体は、原則として国への届出は不要です。ただし、レベル1やレベル2の建材を撤去する場合は、労働基準監督署などへの届出が必須となるため、調査結果の正確な把握が求められます。
ステップ3:作業場所の養生と周辺への配慮
除去作業中にアスベストの粉じんが外部へ漏れ出さないよう、作業場所をビニールシートなどで隔離する「養生」を行います。レベル3は発じん性が低いため、レベル1・2ほど厳重な隔離は求められませんが、作業内容に応じて適切な養生が必要です。
また、作業を行う前には、見やすい場所に「アスベスト除去作業中」であることを示す掲示を行います。これは、作業員や関係者以外が誤って立ち入ることを防ぐための重要な措置です。
あわせて、工事開始前には近隣住民への挨拶回りを行い、工事内容や期間について丁寧に説明しておくことが、後のトラブルを防ぐ上で非常に効果的です。
ステップ4:除去作業(湿潤化と手ばらしが原則)
いよいよ除去作業に入ります。レベル3の撤去で最も重要な原則は、「湿潤化」と「手ばらし」です。
- 湿潤化: 除去する建材に、散水や噴霧器などで十分に水や薬剤をかけて湿らせます。これにより、粉じんの飛散を大幅に抑制することができます。
- 手ばらし: 電動工具などを使うと建材が破損し、粉じんが飛散しやすくなります。そのため、できる限り手作業で、建材を割ったり砕いたりしないよう、丁寧に一枚ずつ取り外していくのが基本です。
作業員は、法令で定められた適切な保護具を必ず着用します。具体的には、粉じんを吸い込まないための防じんマスクや、身体に付着させないための保護衣などです。
ステップ5:清掃と廃棄物処理
除去作業が終わったら、取り残しがないかを入念に確認し、作業場所の清掃を行います。
撤去したアスベスト含有建材は、「石綿含有産業廃棄物」という特別管理が必要な廃棄物として扱われます。そのため、他の解体ゴミとは厳密に区別し、飛散しないように二重に袋詰めしたり、シートで覆ったりして厳重に梱包しなければなりません。
これらの廃棄物は、許可を得た専門の収集運搬業者が、適切な最終処分場まで運搬します。この際、排出事業者(通常は元請業者)は、廃棄物が正しく処理されたことを証明する産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行し、その流れを管理する義務があります。
ステップ6:作業記録の作成と保管
最後に、ここまでの作業内容を記録としてまとめ、保管します。これも法律で定められた義務の一つです。
記録には、以下の内容を含める必要があります。
- 事前調査の結果
- 作業計画書
- 作業開始前、作業中、作業後の現場写真
- 作業員の氏名
- 廃棄物処理の記録(マニフェストの控えなど)
これらの記録は、工事完了後3年間保管することが義務付けられています。万が一、後から問題が発生した場合に、適切な作業が行われていたことを証明するための重要な証拠となります。
以上が、アスベストレベル3撤去作業の基本的な6ステップです。この一連の流れを一つひとつ確実に実行することが、あなたと社会の安全を守るための鍵となります。
アスベストレベル3の撤去に届出は必要?不要?判断フローチャートで一発解決
「アスベストレベル3の撤去って、役所に届出はいるんだっけ?」
解体工事を進める上で、多くの方が悩むポイントです。
しかし、これにはいくつかの重要な例外があり、「不要だと思っていたら実は必要だった」という事態に陥るケースも少なくありません。
その理由は、2022年4月から義務化された「事前調査結果の報告」と、レベル1・2で必要な「作業計画の届出」が混同されやすいためです。さらに、「みなし工事」として扱う場合や、自治体が独自に定めている条例によってルールが異なる場合があるからです。
このセクションでは、あなたのケースで届出が必要か不要かを一発で判断できるフローチャートを用意しました。ぜひご活用ください。
【図解】レベル3撤去の届出要否判断フローチャート
以下の質問に「はい」か「いいえ」で答えていくだけで、届出が必要かどうかを簡単に確認できます。
【フローチャートの質問項目】
- 質問1:アスベストの事前調査は実施しましたか?
- はい → 質問2へ
- いいえ → 事前調査は全ての解体・改修工事で義務です。まず調査を実施してください。
- 質問2:事前調査の結果、アスベストレベル3建材「あり」と確定しましたか?(分析調査を含む)
- はい → 質問3へ
- いいえ(調査で判断できず、「みなし」で工事する) → 「届出」が必要になる可能性が高いです。詳しくは次の「注意!『みなし工事』は届出が必要になるケース」をご覧ください。
- 質問3:工事を行う自治体に、レベル3に関する独自の上乗せ条例はありますか?
- はい → 条例に従い、「届出」が必要な場合があります。必ず自治体の環境課などへ確認してください。
- いいえ(または、不明) → 原則として、国への「届出」は不要です。ただし、事前調査結果の「報告」は別途必要になる場合があります。
注意!「みなし工事」は届出が必要になるケース
事前調査でアスベストの有無が判断できない場合、「アスベスト含有あり」とみなして工事を進めることがあります。これを「みなし工事」と呼びます。
一見、分析費用が節約できて合理的に思えるかもしれません。しかし、安全を最優先するため、法律では「みなし工事」の場合、最も厳しい基準であるレベル1(発じん性が著しく高い)に準じた飛散防止措置を講じるよう求められることがあります。
レベル1相当の措置となると、作業計画の届出義務も発生します。つまり、「レベル3だろう」と自己判断して「みなし工事」を選択した結果、本来は不要だったはずの届出が必要になり、作業全体のコストや手間が増えてしまうリスクがあるのです。
迷った場合は、費用をかけてでも分析調査を行い、アスベストの有無とレベルを確定させることが、結果的に最も安全かつスムーズな進行に繋がります。
外部リンク: 厚生労働省 「石綿総合情報ポータルサイト」
基本的には届出不要と覚えておきつつも、必ずこのフローチャートで例外に当てはまらないかを確認する習慣をつけましょう。少しでも不安や疑問が残る場合は、私たちのような専門知識を持つ業者や、管轄の自治体に問い合わせるのが最も確実な方法です。
アスベストレベル3の撤去費用はいくら?費用相場と安く抑える3つのコツ
アスベストレベル3の撤去費用は、使用されている建材の種類や面積、作業の難易度によって大きく変動し、数万円から数十万円までと幅があります。そのため、「決まった価格」というものは一概には言えません。
しかし、費用の内訳や相場感を事前に把握し、これから紹介するいくつかのコツを実践すれば、費用を適正な価格に抑えることは十分に可能です。
【建材別】アスベストレベル3の撤去費用相場
アスベストレベル3に該当する建材は多岐にわたりますが、ここでは代表的な建材の撤去費用相場をご紹介します。
| 建材の種類 | 費用相場(/㎡) | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| スレート屋根 | 2,000円~8,500円 | 足場の設置が必要になる場合が多く、その費用が別途かかることがあります。屋根の形状や勾配によっても費用は変動します。 |
| ビニル床タイル(Pタイル) | 2,000円~10,000円 | タイルを剥がす手間や下地処理の状況によって費用が変わります。接着剤にもアスベストが含まれている場合があり、注意が必要です。 |
| サイディング(外壁材) | 2,000円~8,000円 | 屋根と同様に足場が必要になるケースが多いです。建物の高さや形状によって費用が変動します。 |
| けい酸カルシウム板 | 3,000円~20,000円 | 内装材として使われることが多く、比較的撤去しやすいですが、狭い場所での作業は費用が上がる傾向にあります。 |
費用を適正価格に!安く抑えるための3つのコツ
「少しでも費用を抑えたい」と考えるのは当然のことです。ここでは、不当に高い費用を支払うリスクを避け、適正価格で工事を行うための3つの具体的なコツをご紹介します。
コツ1:複数業者から相見積もりを取る
最も重要かつ効果的な方法が、複数の業者から見積もり(相見積もり)を取ることです。
最初に提示された1社の見積もりだけで契約してしまうと、その金額が適正なのか判断できず、高値で契約してしまうリスクがあります。実際に、業者によって見積金額に数十万円の差が出ることも珍しくありません。
複数の業者から見積もりを取ることで、
- 自宅のケースにおける費用相場がわかる
- 各社の提案内容や担当者の対応を比較できる
- 悪徳業者を見抜く判断材料になる
といったメリットがあります。手間はかかりますが、このひと手間が最終的に数十万円単位の節約に繋がる可能性があるのです。
コツ2:自治体の補助金・助成金制度を活用する
お住まいの自治体によっては、アスベストの調査や除去工事に対して補助金・助成金制度を設けている場合があります。
これらの制度を活用できれば、費用の負担を大きく軽減できます。補助の対象となる工事内容や金額、申請条件は自治体によって様々です。まずは、ご自身の建物がある市区町村のウェブサイトを確認してみましょう。
「〇〇市 アスベスト 補助金」といったキーワードで検索したり、自治体の環境課や建築指導課に直接問い合わせたりするのが確実です。
コツ3:解体工事全体で依頼し効率化を図る
もし建物の解体を予定しているなら、アスベストレベル3の撤去だけを別の業者に依頼する「分離発注」ではなく、解体工事全体をまとめて一つの業者に依頼する方が、総額で安くなるケースがほとんどです。
なぜなら、
- 足場や養生シートを解体工事と共用できる
- 重機の回送費や人件費を効率化できる
- 業者の管理コストが削減できる
といった理由から、トータルでの費用を抑えることができるからです。撤去と解体を一貫して行うことで、工事全体のスケジュール管理もスムーズになります。
アスベスト撤去の実績が豊富な解体業者に依頼することで、安全かつ効率的に工事を進めることができるでしょう。
【実録】初めてのアスベスト撤去|施主Aさんの体験談から学ぶ注意点
専門用語や法律の話が続くと、「自分にできるだろうか…」と不安になりますよね。ここでは、実際に老朽化したご実家の解体を決意し、初めてアスベストレベル3の撤去に直面した施主Aさんの体験談をご紹介します。
Aさんも最初は、あなたと同じように大きな不安を抱えていました。ネットで情報を集めれば集めるほど、「何から手をつければいいのか」「悪徳業者に騙されたらどうしよう」という恐怖が募るばかりだったと言います。Aさんの実体験から、失敗しないための重要な注意点を学んでいきましょう。
不安の始まり:見積書にあった「石綿含有建材処理費」
Aさんが最初に行ったのは、昔から付き合いのある地元の工務店に見積もりを依頼することでした。数日後に出てきた見積書を見て、Aさんは首を傾げます。そこには「石綿含有建材処理費 一式 350,000円」という項目があったのです。
「この項目は何ですか?」と尋ねても、「スレート屋根にアスベストが入っているので、その処分費用ですね。決まりなので」という少し曖昧な返答しか得られませんでした。どのくらいの量で、どのような作業が含まれていて、なぜこの金額なのかが全く分からず、Aさんの不安は一気に高まりました。「言われるがままに支払うしかないのか…」と、途方に暮れてしまったそうです。
転機:一括見積もりサイトでの出会い
このままではいけないと感じたAさんは、インターネットで情報収集を再開し、私たち「解体工事.com」の一括見積もりサービスを見つけました。藁にもすがる思いで問い合わせをすると、すぐに専門のコンサルタントから連絡があり、Aさんの状況を丁寧にヒアリングしてくれたのです。
その後、Aさんの地域に対応できる優良業者3社から、相見積もりを取得することができました。驚いたのは、各社の対応の違いです。
- B社: 現地調査を丁寧に行い、どの部分にどのくらいのレベル3建材が使われているかを写真付きで報告してくれた。
- C社: 見積もりの内訳が非常に細かく、養生費用や運搬費用なども明確に記載されていた。
- D社: 少し高めだったが、近隣への挨拶回りや工事中の進捗報告など、サポート体制の手厚さをアピールしてきた。
何より心強かったのは、「解体工事.com」のコンサルタントが常に間に入ってくれたことでした。「Aさんの場合、B社の提案が最もコストと内容のバランスが取れていますね」「C社のこの項目は、もう少し詳しく説明してもらいましょうか」と、専門家の視点でアドバイスをくれたおかげで、Aさんは冷静に各社を比較検討できたのです。
学んだ教訓:Aさんが語る「これから撤去する人へのアドバイス」
最終的にAさんは、説明の分かりやすさと実績が決め手となり、B社に工事を依頼しました。工事は計画通りに進み、作業中の写真報告などもあったため、最後まで安心して見守ることができたそうです。無事に解体を終えたAさんは、こう語ってくれました。
「もし最初の工務店だけで決めていたら、きっと後悔していました。複数社の話を直接聞くことで、見るべきポイントが自然と分かってきたんです。何より、専門のコンサルタントの方が中立的な立場で相談に乗ってくれたのが、精神的に一番の支えになりました。これから撤去を考えている人には、絶対に『1社だけで決めないで』と伝えたいですね。」
Aさんのように、最初は誰もが不安でいっぱいです。しかし、正しい情報を集め、信頼できるパートナーを見つけることで、アスベスト撤去は決して怖いものではありません。Aさんの体験は、そのことを明確に示してくれています。
【最重要】失敗しない業者の選び方|不動産コンサルタントが教える5つの確認事項
アスベストレベル3の撤去工事は、どこに頼んでも同じというわけではありません。実は、業者選びの成否が、工事全体の9割を決めると言っても過言ではないのです。
ここでは、数多くの解体現場を見てきた不動産コンサルタントの視点から、信頼できる優良業者を見極めるための「5つの確認事項」を具体的に解説します。
- [ ] 1. 必要な許可や資格を保有しているか
- [ ] 2. アスベスト除去工事の実績は豊富か
- [ ] 3. 詳細で透明性のある見積書を提示するか
- [ ] 4. 損害賠償保険に加入しているか
- [ ] 5. 質問や不安に真摯に答えてくれるか
確認事項1:必要な許可や資格を保有しているか
まず、大前提として工事に必要な許可や資格を持っているかを確認しましょう。これらを持たない業者は、いわば無免許で車を運転するようなもので、絶対に依頼してはいけません。
最低限、以下の3点は必ず確認してください。
- 解体工事業登録: 解体工事を行うために必須の登録です。
- 産業廃棄物収集運搬業許可: 撤去したアスベスト建材を運搬するために必要な許可です。
- 石綿作業主任者の在籍: アスベスト除去作業を現場で指揮する国家資格者がいるかを確認します。
これらの許可証や資格者証のコピーを提示してもらうのが最も確実な方法です。提示を渋ったり、曖昧な返事をしたりする業者は注意が必要です。
確認事項2:アスベスト除去工事の実績は豊富か
アスベスト除去は、経験がものを言う非常に専門的な工事です。特にレベル3は建材の種類も多く、それぞれの特性に合わせた適切な作業が求められます。
業者のホームページで施工事例を確認したり、直接「レベル3のアスベスト除去工事の実績はどれくらいありますか?」と質問したりしてみましょう。
経験豊富な業者であれば、過去の事例を交えながら、あなたの現場に最適な工法を提案してくれるはずです。
確認事項3:詳細で透明性のある見積書を提示するか
見積書は、その業者の信頼性を測るための重要な判断材料です。
信頼できる業者の見積書は、以下のように項目が細分化されています。
- 事前調査費
- 養生費(シート、テープなど)
- 除去作業費(建材の種類、面積、単価)
- 廃棄物運搬処理費(アスベスト、その他廃棄物)
- 諸経費
各項目で単価や数量が明確になっていれば、何にいくらかかるのかが分かり、納得して依頼することができます。
確認事項4:損害賠償保険に加入しているか
どれだけ優良な業者でも、工事に「絶対」はありません。万が一、作業中に隣家の外壁を傷つけてしまったり、想定外の事態で物損事故が発生してしまったりする可能性はゼロではないのです。
このような不測の事態に備え、業者が「損害賠償責任保険」に加入しているかは必ず確認してください。
もし未加入の業者に依頼して事故が起きた場合、その損害賠償を発注者であるあなたが負担しなければならなくなるケースもあります。保険証券のコピーを見せてもらい、補償内容や期間が有効であるかを確認しておくと、より安心です。
確認事項5:質問や不安に真摯に答えてくれるか
最後に、技術や書類だけでなく「人」としての対応も非常に重要です。
アスベストのことは、分からなくて当たり前です。あなたの初歩的な質問や漠然とした不安に対して、専門用語を並べるのではなく、あなたの目線に立って丁寧に説明してくれる担当者かどうかを見極めましょう。
- こちらの話をしっかり聞いてくれるか
- 質問に対する回答が明確で分かりやすいか
- リスクやデメリットについても正直に話してくれるか
このようなコミュニケーションを通じて信頼関係を築ける業者こそ、最後まで安心して工事を任せられるパートナーとなります。
これら5つのポイントをすべてご自身で確認するのは、時間も手間もかかり大変です。
しかし、「解体工事.com」では、ご紹介する全ての業者がこれらの基準をクリアしていることを事前に確認済みです。安心して、あなたに最適な一社を見つけるお手伝いをします。
アスベストレベル3撤去に関するよくある質問(FAQ)
アスベストレベル3の撤去に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。専門家がわかりやすくお答えしますので、ぜひ参考にしてください。
Q. レベル3の撤去に養生は本当に必要ですか?
A. 原則として、レベル1や2のような大掛かりな隔離養生(作業場所を完全に密閉すること)は必須ではありません。しかし、作業内容によっては養生が必要になるケースがあります。
レベル3の建材は、通常の状態ではアスベストが飛散しにくい固い素材でできています。そのため、手で丁寧に剥がす作業であれば、大規模な養生は不要とされています。
最終的な判断は現場の状況によりますので、必ず専門業者に確認してもらうことが重要です。
Q. レベル3は手ばらしでしか除去できませんか?
A. はい、アスベストの飛散を最小限に抑えるため、建材の原形を壊さないように手で丁寧に剥がしていく「手ばらし」が原則です。
電動のこぎりやグラインダーといった工具を使うと、建材が砕けて大量のアスベストが空気中に舞い散ってしまう危険性が高まります。そのため、環境省のマニュアルでも、できる限り手作業での除去が推奨されています。
どうしても手ばらしが難しく、電動工具を使わなければならない場合は、以下のような特別な対策が必要です。
- 湿潤化の徹底: 作業する場所を十分に水や薬剤で湿らせ、粉じんが舞い上がるのを防ぎます。
- 集じん機付き工具の使用: 発生した粉じんをその場で吸い取る機能がついた専用の工具を使用します。
これらの対策を講じずに安易に電動工具を使用する業者は、安全管理意識が低い可能性があるため注意が必要です。
Q. 撤去したアスベストの廃棄方法を教えてください
A. 撤去したアスベストレベル3の建材は、「石綿含有産業廃棄物」として法律に基づいた特別な方法で処分しなければなりません。家庭ごみや通常の産業廃棄物とは全く異なる扱いになります。
処分の流れは、大きく分けて以下のステップで行われます。
- 分別・梱包: 他の廃棄物と絶対に混ぜず、丈夫な袋で二重に梱包するか、密閉できる固い容器に入れます。
- 表示: 梱包した袋や容器には、「石綿含有産業廃棄物」であることがわかるように、決められた表示をします。
- 収集・運搬: 「産業廃棄物収集運搬業(石綿含有産業廃棄物を含む)」の許可を持つ専門業者が、専用の車両で運搬します。
- 中間処理・最終処分: 許可を受けた中間処理施設や、厳重に管理された最終処分場へ運ばれ、埋め立てなどの方法で処分されます。
Q. 作業するのに特別な資格は必要ですか?
A. はい、アスベストの撤去工事には、法律で定められた専門資格を持つ人が必ず関わらなければなりません。主に2つの重要な資格があります。
- 石綿作業主任者(いしわたさぎょうしゅにんしゃ)
除去作業を行う現場で、作業員が安全に作業できるように指揮・監督する役割を担います。作業計画の作成や、保護具が正しく使われているかのチェックなど、現場の安全管理全般を担当する重要な資格です。
- 石綿含有建材調査者(いしわたがんゆうけんざいちょうさしゃ)
2023年10月から、建物の解体・改修工事前の事前調査は、この資格を持つ人が行うことが義務化されました。図面や目視、分析などを通じて、建物にアスベストが使われているかどうかを正確に判断する専門家です。
参考記事: レベル3の解体工事に必要な資格とは?石綿作業主任者と調査者の役割を解説
これらの資格者が在籍しているかどうかは、信頼できる業者を見極めるための非常に重要なチェックポイントです。
Q. 一括見積もりを依頼するとしつこい営業はありませんか?
A. ご安心ください。『解体工事.com』では、お客様が不快に感じるような、しつこい営業活動は一切ございません。
私たちが大切にしているのは、お客様と優良業者との間に立ち、中立的な専門家として最適なマッチングをお手伝いすることです。
お客様からお問い合わせいただくと、まずは専門のコンサルタントが状況やご要望を丁寧にお伺いします。その上で、お客様に最適な優良業者を複数選定し、業者とのやり取りを調整いたします。業者から直接、一方的に何度も連絡が来るようなことはありませんので、初めての方でも安心してご利用いただけます。
アスベストレベル3の撤去は専門知識を持つプロへの相談が成功の鍵
ここまで見てきたように、アスベストレベル3の撤去作業は、複雑な法令や専門的な知識が絡み合うため、個人や一般の業者だけで完璧に対応するのは非常に困難です。
なぜなら、事前調査から作業計画、届出の要否判断、適切な除去方法、廃棄物処理、そして信頼できる業者選びまで、判断を誤る可能性のあるポイントが多数存在するからです。たった一つのミスが、アスベストの飛散による健康被害や法令違反といった、取り返しのつかない大きなリスクに繋がる可能性があります。
しかし、ご安心ください。私たち「解体工事.com」では、長年の経験を持つ不動産コンサルタントが、お客様と優良業者の間に立つ中立的な立場で、最適な解体プランをご提案します。アスベストに関する漠然とした不安の解消から、複数社の複雑な見積もりの比較、専門的な内容の交渉まで、すべて私たちにお任せいただけます。
「解体工事.com」が選ばれる理由
- 中立的な専門家がサポート: お客様の立場に立ち、業者とのやり取りを円滑に進めます。
- 複数社の見積もりを比較検討: 適正価格で質の高い工事を実現できます。
まずは無料の一括見積もりで、あなたの状況を私たち専門家にお聞かせください。複数の優良業者からの提案をじっくり比較し、ご納得いただける最適な一社を見つけるお手伝いをします。
まとめ:アスベストレベル3の正しい撤去方法を理解し、安全な解体工事を
本記事では、アスベストレベル3の定義から、具体的な撤去方法、費用相場、そして最も重要な業者選びのポイントまで、網羅的に解説しました。正しい知識を持つことが、安全で安心な解体工事を実現するための第一歩です。
アスベストレベル3の撤去を成功させる鍵は以下の4つです。
- 手順の遵守: 事前調査から記録の保管まで、定められた6つのステップを確実に実行する。
- 届出の判断: 原則不要ですが、「みなし工事」や自治体独自の条例など、例外的なケースを確認する。
- 費用の適正化: 複数業者からの相見積もりを取得し、内容と金額を比較検討する。
- 業者の選定: 許可や実績、保険加入などを確認し、信頼できる専門業者に依頼する。
アスベストレベル3は、レベル1や2に比べて発じん性が低いため、危険性が軽視されがちです。しかし、、法令で厳しく規制されている有害物質であることに変わりはなく、取り扱いを誤れば健康被害につながるリスクもゼロではありません。だからこそ、定められた手順に沿った適切な対応が不可欠なのです。
改めて、安全な撤去工事のために必ず押さえておきたいポイントを振り返りましょう。
- 撤去作業は全6ステップの遵守が鍵: 「①事前調査」「②計画・届出」「③養生」「④除去」「⑤清掃・廃棄」「⑥記録」のどの工程も省略できません。
- 届出は原則不要、でも確認は必須: 基本的に国への届出は不要ですが、自治体の条例など例外ケースがあるため、必ず専門家や行政に確認しましょう。
- 費用は複数社の見積もり比較で適正化: 1社だけの見積もりで決めず、複数の専門業者から提案を受けることで、適正な価格とサービスを見極められます。
- 最も重要なのは信頼できる専門業者選び: 最終的な工事の質と安全性は、業者選びで決まります。安さだけで選ばず、実績や資格、担当者の対応をしっかり見極めることが重要です。
あなたのアスベストに関する不安が解消され、安心して工事を進められるよう、「解体工事.com」が全力でサポートします。業者選びのお悩みから、見積もりの比較、工事に関する疑問まで、専門のコンサルタントが中立的な立場でアドバイスいたします。
まずは、無料の一括見積もりからお気軽にご相談ください。